
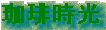
下町に残る昭和の世界というか、やはり小津安二郎の世界を愛したこの監督だからなのかもしれないけれど、そういう意味での懐かしい風景がふんだんに使われてて、そして出てくる日本語がなんとも優しい。
”ちょうだいします”とか”お疲れがでないようにね”とか、場面場面のふっとした時にでてくる日本語が心地よさを運んできます。
映画自体も大きな盛り上がりはなく、ましてや主人公の二人もべらべら話すキャラでもないので、とっても淡々と映画がすすんでいくんだけれど、どきっとするセリフもかなり淡々と語られていくんですね。妊娠してるとか、実の母親じゃないとかっていう、普通だったらすごく大袈裟にとりあげられそうな事がなんか一青窈の雰囲気もあるのかもしれないけれど、さらっと流されててこっちがドキっとしてしまうくらい。
映画初主演の一青窈は演技がうまいのかどうなのかはよくわかりません。演技じゃなくて素のままでてるって感じ。スクリーンの中で普通に生活しているというか・・・。
映像を見てると、日常のなんでもない世界が広がってる感じで、とてもとても懐かしい思いがするのはなぜなんでしょうね。夏の東京のアスファルトから照りつけられる熱さとか、店の中に差し込む道路からの反射したキラキラした光や電車の音などなど、この映画はそういった普段なにげなく聞きながら目にしながら、気にとめてない景色、音色に息をふきこんで語らせてるような気がします。
彼女の実家は上信電鉄をのった先にある設定になっているんだけれど、この電車がまたすごーくローカル。お母さんがご飯をつくって待っててくれて、「おかえり〜、ただいまー」という”家”の日常の風景がスクリーンにあふれてます。お母さんがお父さんにおつまみを出す時の、箸おきやお箸の向きをそろえるしぐさなんて、日本の心だなあ〜としみじみ実感してしまいますね。小林稔二もいい味をだしてるんです。娘のことを心配してるのに口に出せない寡黙な父親。あってますねー。
映画では音楽がほとんど流れてきません。自然の音がいっぱい。家の中の音、街の音、人の会話、畳のこすれる音、雷の音、等等。しかも最後は電車の音が重なり合って、音楽になっていくんですよね。
東京ででてくる喫茶店も渋いです。古い純喫茶っていうのかな。レトロな喫茶店。喫茶店が珈琲の出前をしてくれるなんて、今時少ないですよね。下町の生活にとけこんでる日常。
それにしても東京って電車の音がいっぱいなんですね。東京の音というのは電車の音かも。そこにいると全然わからないけれど、やっぱり外国の人という視点で見るから、日本人だとあまり気づかない光景を感じられるのかもしれません。
一青窈演じる陽子は江文也という人についての取材をしてるわけなんだけれど、映画の中ではその江文也の奥さんが特別出演していて、で、二人のなれそめとか仲のよかった様子を話してるんですが、そこでその奥さんが
”今の時代、私たち二人のような夫婦の話をするとつくり話のように聞こえるかもしれませんが、本当のことなんですよ”
といってる箇所がありました。世の中にはいろんな人たちがいるけれど、でも本当にこの人たちのように何年たっても愛しあえてるようなめぐりあいの人たちっているんですよね。一青窈演じる陽子と浅野忠信演じる肇もそういうめぐりあいの二人なのかもしれません。自分がみた夢の話をすると、その夢について関連することを調べてくれる。自分がいきたい喫茶店があるという話をすると、”じゃ〜一緒に探してみようか”といってくれる。これがききたいといえばすぐそのCDがきける機械をだしてきてくれる。そういう、相手のために何かすることが、お互い何気なく普通にできる関係って憧れますね。
最後のシーンで現れる、丸の内線と中央線と総武線の三つが神田川の上で交差してる景色は、なんというか”こんな景色もあったんだ・・”という新鮮な驚きでいっぱいになります。
あの風景、是非ともいつかみてみたい!
